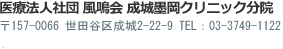成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2026年03月02日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-14-
私にしたところで、たとえそれが一片の幻想にすぎないにしろ、医療の現場で真に革新的な闘争をおしすすめるということを大学の場で一致した時点で(それ以外の闘いの実質はことごとく粉砕させられた時点で)、遂に医師という存在として歩きはじめたのだ。しかし、現在、昔の仲間の一体誰が闘争を担っていけるというのだろうか。
離人症の患者の内部で分裂していくものが《自我意識》だとするなら、時代の内部で深く深く分裂していったものは一体何なのだろうか。
だからこそ、私達は表現の場を求めている。人間のものとして、私達の生きている限りのものとして表現の場は要求されているのだ。そして、そこではあらゆる、人間に関する幻想を解体させなければならない。おびただしい《ひらきなおり》の羅列こそ、私達のものなのだ。
「その認識は我々に、我々の時を愛させる。我々の時とは、知覚させる最も小さな物のようにーーシャボン玉のように、波のようにーーあるいは最も簡単な対話のように、世界の混沌と秩序のすべてをその中に分割されていないままに包含するものだ」(メルロ・ポンティ)
(Ⅰ詩人論/山本太郎論 つづく・・・)
2025年11月27日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-13-
現在、いまだ新しい現代詩の運動体はどこにも存在しない。これは<表現>にとってさえ実に異例なことではないか。現代詩ほど旧式な表現論しか持ちあわせてはいない私達の表現の形が、他にあるだろうか。現代詩には真に時代との緊張関係を露呈させるものは実にわずかな存在でしかないのである。
山本太郎の存在する位置はこうした困難な問いかけをまる捉えしたところにある訳で、彼自身のおびただしい、叫びにも似た問いかけの言葉は単に山本太郎の詩、一篇の詩の完成のためにある訳ではない。
ある日とつぜん
私は旅をはじめていた
鞭のように鳴る肉体を過ぎ
恋のめまいを過ぎ
蜜の巣の子供達を過ぎ
四○年歩いていつのまにか
夕焼のようにひろがる
徒労にとどいていた
頂上を渡る死の
酸性の風よ
この日ごろ私は
祈りのかたちに畳まれ
小さな舟のように流れていった
ちち・ははをしきりに想う
遠さがある
星よりも遠く
私のなかに
遠さがある (「遠さがある」)
例えば、離人症の患者が、ある時点から突然に世界の変転を経験し、総ての自己の感覚・知覚に対して深い(本質的な)疑惑と恐怖を抱きはじめるように、私達にとってある時点から突然にこの時代は変化しつつあったということは言えないだろうか。
学問は退廃し、大学は管理され、表現は掌握され、まさに私達の声なき声はどこまでも拡散して、どこからも返ってこない。一九六八年より以前、誰も今日の厳しい風化のことを予想するものはいなかった。そして、現在ではもはや、あの数年前の闘いの質に触れるものさえいない。
日常性の中に闘争そのものを持ち込むことなど出来はしなかったのだ。
(Ⅰ詩人論/山本太郎論 つづく・・・)
2025年09月29日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-12-
言葉よ しばらく黙せよ
俺は冒頭の一行を
いっきょに消去し
一ヶの聴道 一管の楽器にかわる
俺を静かにならしはじめるのは風
俺の沈黙が受胎する
わずかに 殺されるものの声だ
もはや<生きる>という措辞はいらぬ
<けれど>を消すとき俺は
ほぼ野放図もなく展開し
死の意図を超えるために
死者達の声を受容しはじめる (「詩法」)
山本太郎という詩人は、おそらく状況から最も遠いところにいる詩人である。だが、にもかかわらず、山本太郎の詩がまぎれもなく状況的であるのは何故なのか。
山本太郎は野たれ死に、ということを常に感覚している詩人であると私は考える。自己を野たれ死にさせるために莫大な心的エネルギーを駆り立てて突き進んでいく詩人である。言うまでもなく、私は野たれ死ぬことの美学を説いている訳ではない。野たれ死ぬことのむなしさ、寂しさ、いやらしさ、悲しさ、これらはもう既に言葉の範疇を超えているのだ。そうではなく、ここ現在の表現をめぐる状況のなかでは、私達は遂には野たれ死ぬということにしか、感性の総てを賭けることはできないのだということを私は述べておきたいのだ。
野たれ死ぬ、ということを意識したとき、すなわち私は野たれ死ぬしかないとき、状況の壁は突き破れないまでも、透明になる。
「ここまで幻想を解体し認識を透徹せしめた時に、はじめてわれわれは反転の弁証法をつかむ。われわれの、今ここにある、一つ一つの関係や、一つ一つの瞬間が、いかなるものの仮象でもなく、過渡でもなく、手段でもなく、ひとつの永劫におきかえ不可能な現実として、かぎりない意味の彩りを帯びる。」(真木悠介)
詩的言語の矮小化という現象は無論いまにはじまったことではない。状況の袋小路に追いやられた<詩人達>の精神的活力は徐々に、無為のものとして朽ち果ててしまうしかないように思われる。
いかなる意味においても、詩の流通機構そのものの機能を、自己のものとして内在化し得なかった現代詩のむなしい拡散状態がある。
言いかえれば、詩を支えるもの、現代詩をめぐる根拠に総体的な衰えが進行しつつあるのだ。
(Ⅰ詩人論/山本太郎論 つづく・・・)
2025年06月26日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-11-
流れてなんかゆかない
こんりんざい あともどりなんかしない
垂直にたちて 今宵は
稚い抗のうたを唄う
やがて夜がくるだろう
夜はあやまりなく俺の瞳を潰すだろう
どうしろというのだ!知らない
僕は大人達にはきかない
その賢さによりて 心臆せる
大人達にはきかない
火のなかの石
石のなかの小さな自由
そんな一番大切なことを言うのに
多少の狂気と若さがいるのなら
そんな時一番大切なことを唄うのに
大きな澄んだ心と眼玉がいるのなら
おれはきく
死をみつめ
きりつまった危機と愛とをみつめ
何物にも代え難い
若さを守る 青年達に
おれはきく
どうすればよいのだ
(「微かな角笛に合せまずタローが唄う」)
だが、時代を真正面から見すえながら生き続けていくことはつらいことである。時代の困難さが増すにつれ、それにみあうだけ精神の側の苦渋も一層激しいものとなっていくだろう。「若さ」というものを軸として、山本太郎の発した「どうすればよいのだ」という一語は永遠に解の存在しない謎の環の中に組み入れられてしまう。状況の側、時代の側の変転と詩人の内部の変遷との間に、言葉もなく懸垂している巨大な影がある。
『歩行者の祈りの唄』から、詩集『死法』にまで至る山本太郎の足跡には、厳しく一つの予感が存在している。山本太郎の詩的行為はこの予感を綾なす糸のように織り込んで連なっている。そして、この予感とは言葉の喪失をめぐる詩人の営為である。しかも、ここ数年山本太郎の予感の激しさは加速度を増し続けていることも確かなことなのだ。果して山本太郎はこのさきどこへ行くのか、という想いが最近の私の頭にこびりついて離れない。ポール・ニザンは何でも言うことができた。私達が耳をおおいたくなる時でさえ、何でも言うことができた。しかし、山本太郎はいま何でも言うことができるのか。
私は、山本太郎が既に老いたという風な話を書こうとしているのではない。老いたというなら時代そのものが既に老いたものとなっていることをまず言わねばならない。私達はいま、このように言葉の喪失にむかって膨大なエネルギーを消費しつつ苦闘している一人の詩人の声に強くひかれる。そして、それがそのまま私にとっては一九六七年と一九七三年の落差なのだ。
(Ⅰ詩人論/山本太郎論 つづく・・・)
2025年05月29日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-10-
山本太郎論
言葉の喪失
詩人はいつまで詩を書き続けるのだろうか。詩人はいつまで詩人であり続けるのだろうか。言葉を失うまで、とは言わせない。おそらく解答としてそれは不適当であろう。状況の中で言葉を失ってしまう詩人もまた確実に詩人であり得ることを私は知っている。
だが何故、詩人は詩人であり続けることよりもはるかに遠い地点で、言葉の喪失に固執しなければならないのだろうか。
詩人にとって、言葉の喪失とは一体なのか。
山本太郎の詩について触れるとき、第一詩集『歩行者の祈りの唄』から出立つしなければならないことは果して当然なのだろうか。
例えば私は想い出す。ポール・ニザンのことを。
「ぼくは二十歳だった。それがひとの一生でいちばん美しい年齢だなどとだれにも言わせまい。
一歩足を踏みはずせば、いっさいが若者をだめにしてしまうのだ。恋愛も思想も家族を失うことも、大人たちの仲間に入ることも、世の中でおのれがどんな役割を果しているのか知るのは辛いことだ。」(『アデン・アラビア』)ポール・ニザンは無論私にとって特別な意味のある人間であった。ポール・ニザンは何でも言うことができた。
「怒りを向けよ。きみらを怒らせた者どもに。自分の悪を逃れようとするな。悪の原因をつきとめ、それを打ちこわせ。」
ポール・ニザンはついに言葉の喪失に出会わないまま死んでいった。だからこそポール・ニザン!という私の内部の声とは別に、ポール・ニザンを遂には私の同時代へとは同化できないもう一つの声がある。
ポール・ニザンを、まだ現在とは比較にならないほどのんびりとした、小さなバリケードの内側で横目で垣間見ていた一九六七年頃私はやはりどうしようもなく『歩行者の祈りの唄』が好きだった。
(Ⅰ詩人論/山本太郎論 つづく・・・)