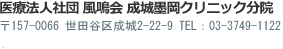成城墨岡クリニック分院によるブログ形式の情報ページです。
2015年12月26日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-129
正常な世界に不満を持つほど、私は正常な人間ではない。どんなに最低の正気でも、狂うよりはましだ。」(小林美代子『蝕まれた虹』)
小林美代子の死が知らされたのは、昭和四八年九月一日だった。死後二週間を経て、三鷹市の自宅で発見された小林美代子の孤独で、いたいたしい死のことについて、私は本来なら何も語るべき言葉を持たない。だが、小林美代子の死には、一人の人間がどのようにも支えきれなかった巨大な設問が宙ずりになっているのだと私は思う。誰もが、問題にすべきであるはずなのに、誰もが、まずはじめにさけていってしまう、表現と状況の壁のことである。
小林美代子の文学的行為は、決して概念的な規範のなかで裁断されるべきものではない。狂気とか、批評とか、完成とか、それらもろもろの商標こそ、実は小林美代子の生をおびやかし、表現の核を砕き割った加害の構造である。
小林美代子の作品は、何故書くか、何故書くかという自らの問いを一方の極点としながら、もう一方の極点では、この問いを発しながら、この問いそのものを支えている自我の存在を見きわめることをもう一つの課題とした二重構造として成立している。
小林美代子の文学はいたましく、おぞましい。だが、そのことは、既に小林美代子という人間の生が個々人の感受性の埒外のものとしていたましいものであったからにほかならない。
自我の存在を見きわめるということが、小林美代子の作品の跳躍の契機となっているというとき、それはこの対極として小林美代子の内部では既に自我が鋭く脅かされている状態にあることを予感している。
「ほとんど睡眠薬で眠っている。睡眠薬の眠りは、黒い鉄板でガッと思考を断ち切ったような闇の、全く自己のない眠りである。電話が鳴りつづけていたような気がする。不意に大きくベルがなる。(中略)
私は電話に引きつけられてしまう。電話の小さい穴から、それが私の責任のように聞える。
また下痢症状が起り始めた。世の人の不幸の責任は全部私にあるように思い始める。電話を放すことは、あちらを放り出すことになる。じりじり握りしめている。私は早くころりと眠りたいと思う。」(蝕まれた虹)
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)