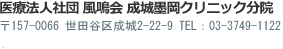成城墨岡クリニック分院によるブログ形式の情報ページです。
2016年01月12日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-130
同人誌「文芸首都」において、はじめて小林美代子の小説に出会ってから、昭和四六年度群像新人賞を得た「髪の花」、そして遺稿である「蝕まれた虹」までの作品に接してみると、これはやはり死ぬべくして死んでいった人間の、他にどのようにも図式化できない命の記録であるように私には思えるのだ。
小林美代子の内で、自我の崩壊をかろうじてくいとめていた書くこと、表現することへの意志は私達にあらためて、表現行為の持つ人間的意味の中核をあきらかにしてくれる。小林美代子の描き出す世界は、おそらく表現論の故郷である。だから、それは本質的に内在的、存在論的な表現の形であるとも言えるのだ。だが、私達が自己の生存の問題について触れるとき、単に小林美代子の作品をこのように位置付けることが私達にとってどのような意味を持つものであるのだろうか。私達が、そもそも作品を位置付けるということは一体何なのか。私達の表現行為は一体何なのだろうか。
ここで、私は一つのことを言いたい。小林美代子の表現行為をささえていた自我の崩壊はとてつもなく内的な事実であることは確かであり、この内的な存在にむかって私達の表現論は突出していかなければならないことも事実である。だがしかし、小林美代子の死はどのようにしても小林美代子の死を拒絶することができなかった<状況>の側の責任であると私は思う。
かつて、江藤淳は群像新人賞の選評で次のように語っていた。
「近頃では、狂人のほうが正常人より純粋だとか、むしろ現代社会の“歪み”が狂人によって告発されているのだというような言説をなす者が、専門の精神科医のなかにさえときおり見受けられる。インテリの寝言とはこのことであって、こういう曲学阿世のともがらは、狂人のなかにひそむ治りたい願望について、一滴の涙すら注ぐことができないのである。単なる安価なヒューマニタリアニズムでこの涙を流すことができないのは、それにもかかわらず狂気というものがはなはだ治りにくいものだからである」(『髪の花』を推す)
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)