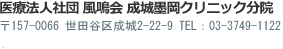成城墨岡クリニック分院によるブログ形式の情報ページです。
2016年11月10日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-143
彼女は地方の高校を卒業するとすぐ、上京し現在の職場に務めた。彼女は故郷があまり好きになれなかった。小さな町での人間関係が漠然と好きでなかったと語ったが、それだけではなく、彼女はあまり母を好きになれなかったのである。
大手銀行の寮に住み込んだ調理師としての仕事は、一五〇人位の男子寮のなかで、最も目立たぬ、地味な仕事場であった。
そこでは自分の務める仕事場と自分の部屋とが同じ屋根の下にあり、プライベートな時間との区別も判然としていなかった。
仕事に対する不満を彼女は用心深く語るのをさけていたが、彼女の置かれた設定の不自然さは明らかであった。
しかし、彼女には職場を変えるだけの積極性も勇気もなかった。新しい環境への適応性もないということを最もよく知っていたのは彼女自身であった。
彼女は、仕事の時間以外は、ほとんど一日中部屋にとじこもり、ボンヤリ(まさにボンヤリ以外のなにものでもなく)時間を過していた。“出口なし”の状態のまま、彼女の激しい欲求のみがつのっていく。
彼女は毎日のように机にむかって、詩を書くか(幼児的な詩を!)、日記をつけていた。日記はかなり激しい調子で自己主張を展開しているもののようであった。
職場のなかでも、寮生活のなかにあっても彼女は常に問題児であった。彼女自身、意識的に規則とか常識に対して反抗するところもあり、職場でも公然と無視されることがたびたびあり、管理面での問題がもちあがると、すぐに彼女が呼びだされて説教されるという具合いだった。彼女には、管理に対抗する思想性はほとんど育ってはいず、彼女をささえていたのは、強固な自我意識と、彼女が自分自身を規定した生き方であった。
このような寮の管理や人間関係に反抗して食事は全然とらないでいる、などという日が当時も続いていた。
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)