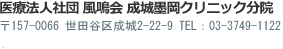成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2015年12月01日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-128
だが、私がこの表現考のなかで把えようとしている現象学的叙述は、いわばこの確固とした体系、そして至るところの判断中止(=アポケー)を包含しているものではない。私の内で現象学は常に「混沌そのものへ」むかう。すなわち、人間の最も否体系的な、否外在的な、そして被表現的な存在の激しい象徴である。
だから、この現象学そのものは必然的に、私達が<状況>と呼びならわしている、社会人間的構造のなかに突出していかざるを得ないのだ。
私達が真に人間的な生存を企図する場合、そしてこの企図のもとに生きながらえるためには、その前に私達が果し得るべき跳躍が措定されなければならない。そして、この跳躍のための準備段階として個人に内在されているものが<表現>そのものであると言ってよいだろう。そして、その<表現>をめぐる解釈学の試みが、私が現象学的叙述と呼ぶところのものなのである。
私がなぜ、人間の表現行為を、おしなべて必要以上に問題としようとするのかは、個人の内面の問題として疎外され、さらに、個人の外在的関係としてとして疎外されるという二重構造に包まれてしまっている、現在の私達の自我の息ぐるしいまでの心のあえぎを、どうしても消し去ってしまってはならないものだと考えるからである。
例えば、私達は実に多くの、私達に関係づけられた人間の死によって私達の実存を規定されている。それらの死は、単に状況のなかでの殉死者達のみを意味するものではない。私達の感性が触れ、私達の生存に深くかかわりあう、至るところの死者達である。
「昼から電燈をつけて毎日向った机、沢山の言葉が浮び、消され、書かれていった。時に絶望し、焦慮し、虚脱感に襲われた。メニエール氏病の目まい止めの薬と水の入ったコップを机に置いて、発作に備えたりした。
その絶望もここでは王冠のように輝いていた。
私の影となった、正気の自分が、そこ、ここで、飯を炊き、机上で、抱かれた処女のようなはじらいと期待で、文章の生まれるのを庭の椿に目を放って待ち、床に座って眠る為のブドー酒を含んでいる。
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)
2015年11月14日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-127
Ⅳ 私的表現考
雑誌『詩学』に48年5月頃から連載をはじめたエッセイであり、私の内なる表現論を外側から支えている日々の行為のなかからの問題提起である。はじめに一般的な表現の問題から書き綴られたが、次第に私がどうしても最も強くかかわらざるを得なかった精神医療の問題に力点が移ってしまった。そのために、ここに収録する時点で『詩学』当時の形を整理してみた。私の気持ちを理解して、詩の雑誌にこのような場違いな論考を長期間に渡って連載することを評してくださった、『詩学』の嵯峨信之さんに深く感謝しています。
表現の現象学
ⅰ
私がこのささやかな論考を、とりとめもなく書き続け始めて、もう何ヶ月かがたつ。私はいつも同じ部屋で、いつも同じ机に向って書き続けてきた。
私の部屋の本箱にある一冊一冊の書物は、無論、私のここ数年間の軌跡であるはずである。そして、この書物の書かれざる空間の背後には、すぎ去って行く時の巨大な姿がある。私は、くる日もくる日も、まるで変化しない私の自我を通りすぎる時間に抱かれたまま、同じようにたちつくしているしかない。
だが、私がこの書くという行為をめぐってたどたどしく逡巡しているとき、私の自我が占拠し得る内部の時間を、そして空間を、まさに軽々と玩具化してしまう<悪霊の時代>があることを知らなければならない。
表現の現象学と私が書いたとき、それは一体何を意図しているのかということが問われるべきである。“現象”とは何か、“学”とは何か。
私は、表現論の現象学的叙述という意味で、表現の現象学と呼んでいる訳なのだが、ここでの現象学の私的意味について触れるべきだろう。
現象学は、すなわち一個の思考、表現論の範疇のなかで、<学>そのものとわかちがたく結びついてきた。それは、常に背後に待機した巨大な体系を予感させるものであったにちがいない。この予感のうえにこそ、「事象そのものへ」(Zn dem Sachen Selbst)という命題は現象学の中核でいかにも多様な人間的解釈を可能にしてきたものだともいえるのである。
(Ⅳ私的表現考/表現の現象学 つづく・・・)
2015年11月01日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-126
しかし、このような悪循環をどのように生存の時間帯の中で割付していくのか、さらには現実の闘いの場をどのように展開していくのかについては、「儀式」では触れられていない。最近作「夏の妹」はこの重い問いかけをひきつぎ、作品の核として成立している。沖縄を描いてあまりにも図式的で皮相的でありながら、また映画構成そのものも常套的で感傷的でもあるこの作品が逆に豊かな示唆を与えてくれる理由もそこにある。
やはりここでも、大島渚の六〇年以後に再生した精神は徐々に衰退していくように見える。だからこそこの映画は、“困難な”状況を宿命として育った若い世代に、新しい伝達の開拓をまじめに託そうとする、表現のありかたの提供である。事実、沖縄を如何に描くかということよりも、何故沖縄を描くかということの方が、はるかに息苦しいことであるような場所に私達はたっている。私は至るところで語りたいのだが、闘いをする、運動をするということは何者に対しても免罪符にはなり得ない。むしろ、現在あらゆる処で必要とされているのは、何故という誠実にささえられた深い問いの力であり、人間への限りないやさしさである。
「夏の妹」には自己破壊への欲求と、自己再生への力とが綾織りにされていて、それが従来までの“父なき家”のための“父探し”の構図をはるかに深く越えている。そしてやはり新しい構図の底にあるものは大地から突き出る新鮮なやさしさである。
大島渚の映画ほど、観る側の立場と、生活と、人間への愛とを明確に浮き彫りにするものは他にない。だから私達は、そう簡単に大島渚の傍をとおり抜けることはできない。
「夏の妹」は語る。
「妹と呼びたい。そして、できればぼくが生れ育った沖縄で君に優しくしてあげたい。」
(Ⅲ映画論/「人生劇場」そして「夏の妹」へ 終わり)
2015年10月15日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-125
六八年から現在までに至る僅かな間に映画表現が突きあたらなければならなかった巨大な壁は、状況と文化をめぐる新しい地平の勃興とその没落と無関係であり得ない。それは極めて精神的・政治的・人間的な暗礁であって単なる風俗の課題ではなかった。加藤泰の変遷の行処を私は厳しく見続けるだろうが、一方この表現にとって苦渋に満ちた状況にあってなおかつ表現を追求することを止めない多くの人々にとって「夏の妹」の大島渚の動向は実に象徴的である。
前作「儀式」で大島渚は彼にとって大きな意識の変革を定着させた。おそらくそれは大島渚の内面で形をとりつつあった表現への不安と状況の不毛との接点に脆く築きあげられた壮大な観念図絵であった。「儀式」での大島渚は、この時代の困難な状況を背負いながら、その状況そのものの困難さの故に結局は自分をのみだめにしていくという、宿命的な悪循環の側に足を踏み込んでしまったと言えるだろう。そして、まさにその根拠から、状況を自己主体そのものを崩壊させていく形でひたすら耐えることによって、闘いを持続させていくことを選んだのだ。だからこそ、カール・メニンジャー流に大島渚は、「 人なみはずれて大酒をのむのも、結局は緩慢な自殺をはかってるのと同じかもしれない。」と語ったりしたのだ。
(Ⅲ映画論/「人生劇場」そして「夏の妹」へ つづく…)
2015年10月01日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-124
いま、加藤泰の「人生劇場」は実に完成した様式美を駆使して存在している。吉良常も飛車角も瓢吉も、宮川もみんな一段と若返りさわやかな青春ドラマとなっている。だが、私はこの「人生劇場」に限らず最近の加藤泰の仕事に強い不満を持っている。加藤泰は映画作家としては非常にすぐれた存在になりつつある訳だが、それに見合うだけ、映画表現を空虚なものにしつつあると言ってよい。本来、加藤泰の映画の持っていた破壊的な力動を失いつつある。加藤泰は言うまでもなく、六〇年以後の映画表現をその職人的な耽美主義によって、また同時に状況のアレゴリーを実に巧みに映像へと転換することによって追求してきた作家の一人である。「三代目襲名」や「男の顔は履歴書」、「懲役十八年」等は状況を実に見事に先取りした、権力への不服従の世界であった。だが、加藤泰の危険性は実は、その初期段階から既に内在していたことも事実であって、かつて私は加藤泰の「真田風雲録」について次のように書いたことがある。「アナロジーは果てしない悪循環の後に俗っぽいパロディとして終わる亜流の思想であり、虚偽であり、偽善であることを告発しなければならない。例えば加藤泰が『真田風雲録』で見せたパロディの無残さは六〇年の死者が、私達を常に弾劾し続ける沈黙の意味にはるかに及ばないばかりでなく、それは状況に対して独力で苦しい闘いを賭している者に対する不逞な挑発であった。」しかし、この「人生劇場」をとりかこんだ空虚は、加藤泰自身の息苦しさの肉声とでも言うべきであって、表現を流通機構の側に委ねてしまわざるを得ない誠実な作家の帰結でもある。「映画監督である以上、『人生劇場』は一度は撮りたいと思っていました。」と語る加藤泰に対しても、この二億八千万円をかけたという大作は場違いなのだ。他の主人公の誰よりも、お袖、おとよの二人が実にたくましく、なまなましく描かれているのも偶然ではない。
(Ⅲ映画論/「人生劇場」そして「夏の妹」へ つづく…)