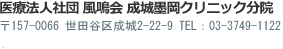成城墨岡クリニックによるブログ形式の情報ページです。
2009年07月26日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-38-
渥美育子自身が、かつて私に語ってくれたように、彼女が事務的な能力においても秀いでているというエピソードは、単に情報処理に卓越した才能を持っている云々、などということでは決してないはずである。より内的な世界を構築している人間こそ、より状況的であるという仮説を私は思い出すのである。ところで、状況の側にある者の人間的基礎は、さまざまな論点から論理化されている。それが例えばここで引きあいに出している大学紛争にしても、ラディカルな側については、一例としてKenneth Kenistonが重層した心理学的機制について述べているのだが……。
「示威行為が抗議者自身の運命の改善に向けられていることがほとんどないことが分かろう。抑圧されている者との一体感の方が、直接に一人ひとり抑圧されているという現実の感覚よりも、より重要な動機づけの要因なのである。」(“The sources of student dissent”)
「ラディカルの発達における中心的課題に戻るならば、ラディカルな関与を支える決定的な力は、たぶん、自分のもつ基本的原則に従って行動しているという内心の感覚である。」(Keniston:“Young Radicals”)
このように分析づけられた心的機制とは相異なる(正反対とは言えぬまでも)内的な関与については、私達の知り得るものは少なかった。
だが、内的な関与という経験が現実である限り、そして私達に人間存在の深淵を垣間みせてくれるものである限り、私達はこのような現実の持つ意味について考え続けなければならない。
そして裏切りとは言葉を核にして
内部の風景を知ることだ
構造の秘密を透視するとき
われわれは最もほしいものを切りすてて
我身を逆方向にひきはがす
われわれは知ることにおいて敗者になり
拮抗する意志を燃えたたせ
絶対を求めて弱体を見る
われわれは無名の寝袋をかき切って
ほとんど自虐の勝者になる
(Ⅰ詩人論/渥美育子の内的世界つづく…)
2009年07月09日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-37-
だから、はじめからことわっておかなければならないが、私の大学紛争についての関与と渥美育子のそれとはまるで大きく異なったものである。思想としても、認識としても、私個人の歴史としても180度対立するものであるかも知れないのである。だが、それにもかかわらず、私がなおかつ渥美育子という詩人について触れなければならないのは、私自身が内的な関与に対して多くの魅力を感じ、どこかで人間の激しい息づかいを感じるからである。かつての、格言めいた言葉の如く、状況から最も遠くに位置する者こそ、最も鋭く状況的である、と私は思わずにはいられない時がある。
それはすべての枠をはずし
輪郭をうちこわす
それは自由を奪うものの自由を奪い
破壊の前方に純白を見ようとする
積みあげられた胃袋のような部屋には
すでに有機体がない
共感、共鳴、交流がない――
百足のようにはしご車によじのぼり
百舌のように仮想の敵を串刺しにする
きみたち
声にもならず
グワーンと
ただグワーンと
天空につきぬける否定
きみたちは骨の髄から滴る痛みで
ひとり語ることがあるか
きみの振りあげた手は
信号系を支配できるか
きみの目は多面の透視体になり
きみの理論は
逆説の坑道を
どこまでも降りてゆけるか
きみたちがやるなら
わたしは居すわる
きみたちが押すなら
わたしが引く
きみたちがやめるなら
わたしが殺る!
(同前)
このような激しい表象は、揺れ動く外的世界に対峙する内部の声である。私にはここに述べられている「きみたち」の声を、まるで異なった声々としてしか聞きとれないという前提があるにもかかわらず、渥美育子が固執しようとしている世界の構造がよくわかる。
詩集『裏切りの研究Ⅰ』のあとがきのなかで
「少しずつ克明に見えてくるイロニーの網目に落ち、もがくほど深くのみこまれてしまう。<裏切り>とはわたしにとってそうしたなかでの内部崩壊であり、憎悪の樹皮に包まれた断念の樹である。」
と述べる渥美育子の詩句は、彼女自身の状況(=Interpersonalなもの)と、内部意識とのあいだの不可避な葛藤によって成立していると考えることができる。
(Ⅰ詩人論/渥美育子の内的世界つづく…)
2009年07月01日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-36-
かつて、渥美育子は山本太郎論の冒頭で次のように述べたことがある。
「神なきあと、人間の情動と闘いつづけている詩人たちの領域に属しているわたくしにとって、神を認識の保塁に置く山本太郎は異質のひとである。」(「原初への開自の唄」)
私は、渥美育子を人間の意識の内部の経験にむかって、その情動を激しく突き立てようとする詩人の一人として理解しようとしている。そこでは、渥美育子という存在が詩という表現へ関与しようとする形態はきわめて、内的な構造をもっているからである。
なぜ一つの言葉、一つの主張
一つの行為、一つの事実
なぜ一冊の本、一人の人
一片の思想、一切れの批判
すると
わたしの中で否定の電流がはねあがり
儀式のように暗号がかえってくる
すべて一点にむかって走る
おびただしい言葉 おびただしい主張
おびただしい行為 おびただしい事実
無数の本 無数の人
無数の思想 無数の批判
そして朝のベッドの中で
手足をもぎとられ 寝袋につめられて
一つの言葉もなくおびただしい言葉もなく
幸福にころがっている
無数で一つの障害物だ
(さあ 動こうかやめようか)
ここからの見通しはすばらしい
その上自分の姿も見えないのだ
脈絡のない断片につながるか
密かに敗者の眼をかちとるか
(「裏切りの研究」)
この「裏切りの研究」という長篇詩には、大学紛争について、という副題がついている。
この、一見して非常に状況的な詩ほど、渥美育子の内的な世界を表出している作品はないというのは一つの逆説だろうか。だが、考えてみれば、大学紛争を状況的作品として表現しようとするとき、私達は個々の具体的な紛争の歴史的=政治的構造を抜きにして作品として抽象することはできないことを感じているのだから、渥美育子の立場は、はじめから異質な背景のもとに成立していると考えてもいい訳である。
(Ⅰ詩人論/渥美育子の内的世界つづく…)
2009年06月24日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-35-
「行動についての非常に多数の単位を寄せあつめ、これらを、非―人間的客体からなる系を構成するところの多様さとなんら異なるところのない仕方で、推計学的な母集団とみなすことはできます。しかし、これでは人間を研究しているのではありません。人間の科学というかぎり、私は自明の理として次のことを言いたいのです。
『行動は経験の函数である。そして経験も行動もともにつねに自分以外の他者ないしは他物との関係の中にある』と。」(R.D.Laing『経験の政治学』)
私は、私自身の表現論という立場から、かならずしも完成された詩や、構成上のイメージにこだわることをやめる。私にとって詩の完成などという問題が意味のあることだと思われないという理由だけでなく、方法的にも私は詩人の意識と、知覚と表象の産物であるところの語句そのものの解釈(主観的解釈)をとおして、心理学的に私達が求めている深層面接(depth interview)を援用したいのである。
(Ⅱ) 内的な関与
渥美育子の詩に出会う者にとって、まず最初に突き当るのは、読者を拒絶するかのような難解なイメージの壁である。渥美育子の詩のこうした難解さが何に由来するものなのか私には正確にはわからない。多分それは、多くの人が指摘するように、渥美育子がまず最初に外国語を使って詩を書きはじめたという事実と不可分のものであるだろう。渥美育子が描き出そうとする言葉の世界は、その背後にある豊富な異質文化への依存を軸にして成立しているようにも思える。だがしかし、単に詩における表現の方法に関する問題だけでなく、この難解さは、渥美育子自身の詩という表現への関与のありかたそのものに関っているように私には思えてならないのである。
何故、詩なのかという問いかけは、それぞれの詩人に対して、主観的・客観的にあびせかけられる設問の基本的に重要な部分を占めているに相違ない。そしてそれは、多分詩とは何かといった使い古された常套句に連なるものなのであろう。
私自身は、表現および表現行為に関して、人間的基礎を求めているのであるけれども、例えば、“関与”の問題を考えるうえで各々の詩人の詩への関与の所在を求めていくのは決して意味のないことではないと考えるのである。
(Ⅰ詩人論/渥美育子の内的世界つづく…)
2009年05月31日
カテゴリー:院長より
見果てぬ夢の地平を透視するものへ-34-
渥美育子の内的世界
(1) 方法的接近
個人の表現行為にかかわる人間学的・現象学的な考察が、私のここ数年来の課題であった。それは単に、精神医学からみた創造の問題ということではなく、私という主観が精神医学への関与(治療・研究・構造・企図・転移etc)を通して得たさまざまな知見と諸理論を基礎として、個々の<人間>の行為を現象学的に<認識>することによって、表現をめぐる個人の内的世界の構造を明らかにすることが目的であった。
だが、私達がここで精神医学と規定するとき、それはむしろ人間の学としての内実を指向し(例えば、Thomas Szaszの“Problems in living”)T.Szaszの述べるように、あたかも巨大な神話として独り歩きしはじめてしまう権威主義的な精神医学でもなければ、疾患をめぐるレッテルはり(labeling)に加担する精神医学でもない。
私達が求める表現論の展開に最も強い刺激を与えたのは、まず第一にR.D.Laingであったことは確かである。Melanie Klein等の自我心理学及び精神発達理論という精神分析の大きな流れからの影響を受けながら、現象学、実存主義への接近(Laingのいう経験の理論experience)、二重拘束理論(Double-bind)、ニューレフトへの傾倒といった幾つかのモチーフを踏み台としてAntipsychiatryというきわめて状況論的色彩の強い主観主義心理学を提唱していったLaingの作業は、表現論の解明であったと言って過言ではない。
(Ⅰ詩人論/渥美育子の内的世界つづく…)